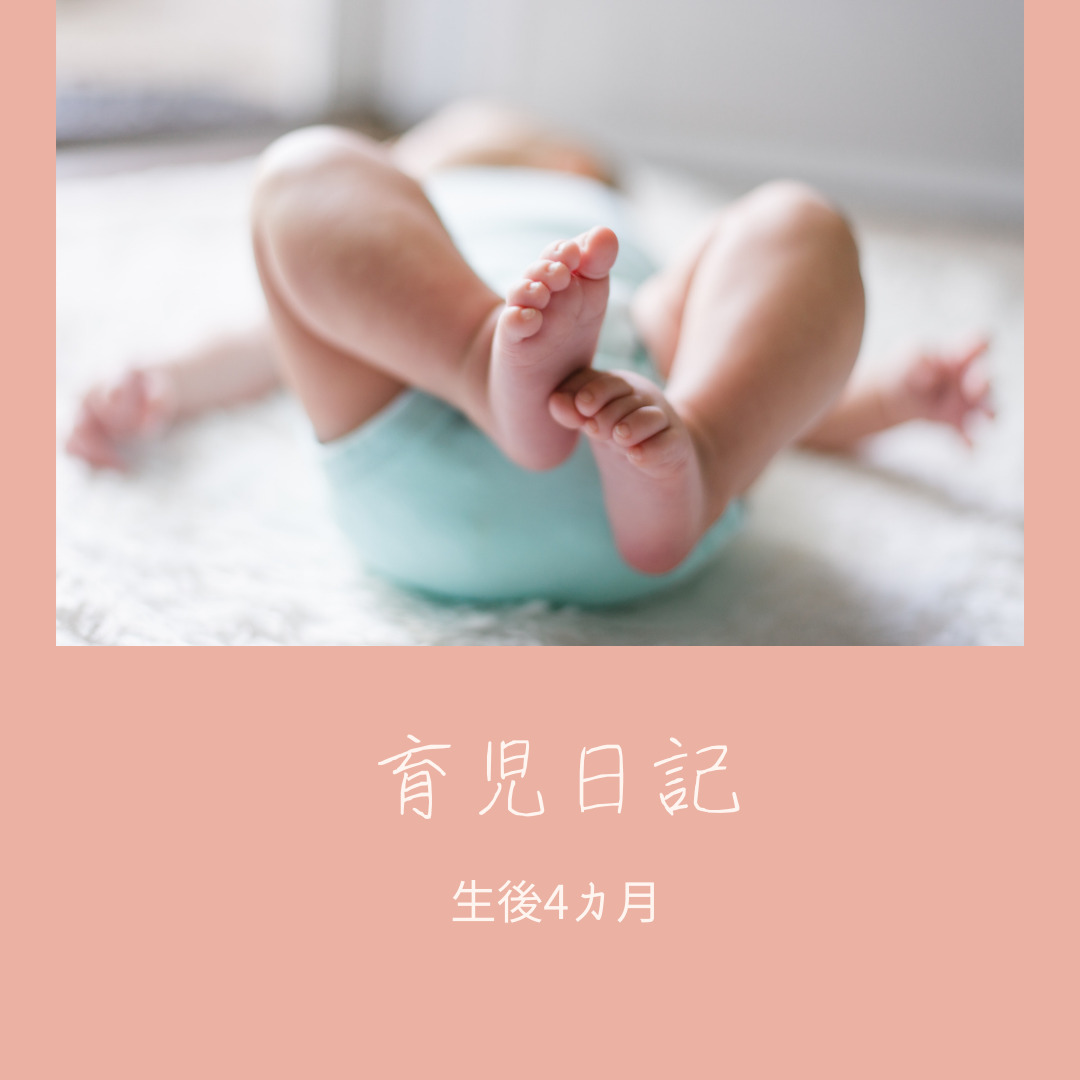今回は生後4カ月の振り返りです。
このころになると、首も完全ではないものの、軽く支えれば大丈夫な程度に座ってきて、吸う力が強く哺乳瓶の先をつぶしてしまうほど。全体的に力強くなりました。
生後1~2カ月の頃のようにぐんぐん身長・体重が増えるわけではないですが、脳が発達するためか頭位が際立って大きくなった気がします。
育ちざかりの4カ月です。
寝返りの兆候アリ、足の力で回転
うちの子どもの場合、おなかの中にいたころから足の力が強く、生まれてからもあお向けながらに足を平泳ぎのような感じでバタバタとしきりに動かしていました。
4カ月になって、単に体に平行に足をばたつかせるだけでなく、地面に突っ張るような仕草を見せるようになりました。
そして次第にその力が強まり、地面を蹴って、くるりと体の向きを回転させるように。
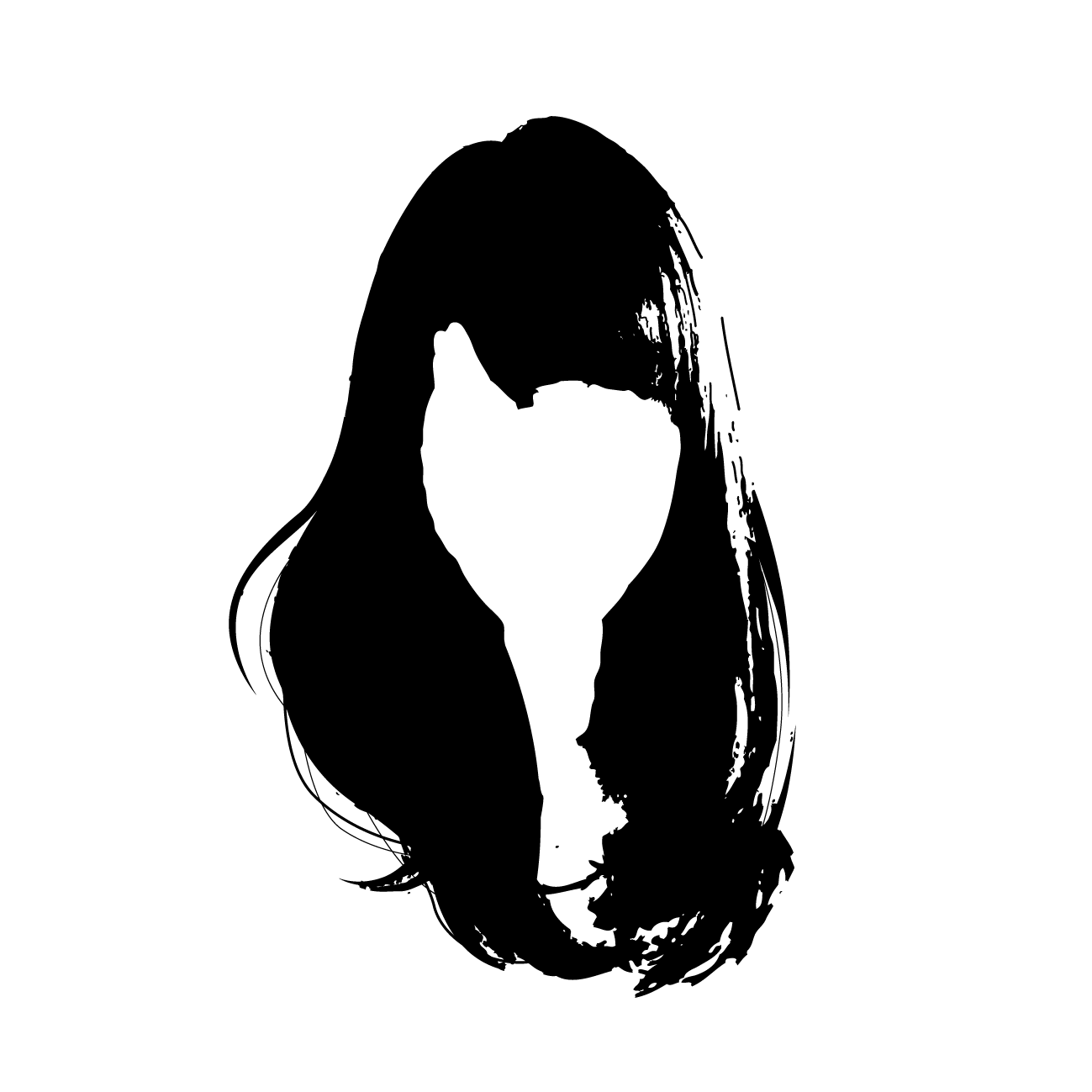
縦向きに寝かせていたはずが90℃回転して横向きになってる…!
ということが多発するようになりました。
昼夜の区別をつけるために、朝起きた後はお昼寝用のコンパクトベッドか大人用の布団かバウンサーの上に寝かせていました。
お昼寝ベッドは赤ちゃんがすっぽり収まるだけの小さなもので、蚊帳のような感じでチャックを閉めておくことができるのですが、抱き上げる際にいちいち開閉するのが面倒で、ずっとめくって開けっ放しにしていました。
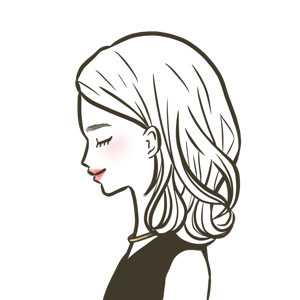
お昼寝用に使っていたのは、西川リビング のミッフィー コンパクトベッドです。
折りたたむこともできるので、片付けや車で帰省する際の持ち運びにも便利です。
そうすると、足の力で回転して横向きになりはみ出してしまうので、お昼寝用コンパクトベッドはもう使えないかなぁという感じになってきました。
そして4カ月半になったあたりで、体をひねる動作もするようになり、調子が良いと一瞬横向きになるようになりました。
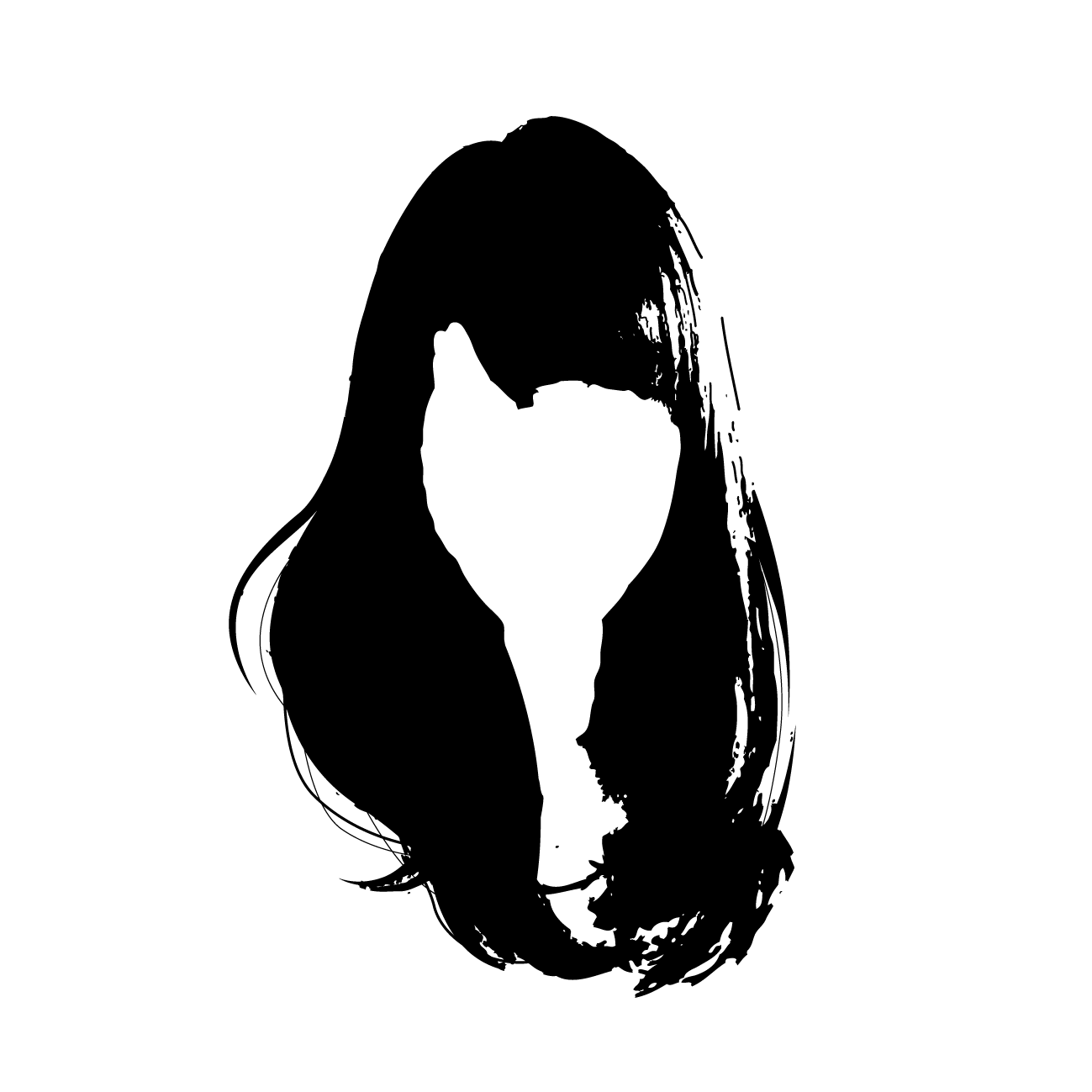
これって、寝返りの前兆…?!
ということで、たまに体を支えて横向きからうつ伏せへの補助をしたり、うつ伏せ遊びをしたりして、寝返り練習のようなこともしてみました。
寝返りをするかどうかは発達段階の目安にはならないそうですし、寝返りし始めたら今まで以上に目を離せなくなるので、今思うと練習してまで早く寝返らせなくても全く問題ないかなと思います。
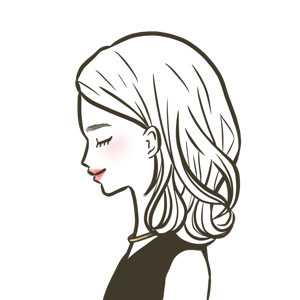
でも、できることが増えて、いろいろな表情を見ると、ちょっと嬉しくなるのが親心なのですかね。
まだ起こして夜間授乳?
授乳回数が授乳量増加に大きな影響を及ぼすという生後100日も過ぎ、夜中は3時間以上眠るようになってきました。
そろそろ子どもが起きなければ、夜続けて眠れるのかな…?と思っていました。
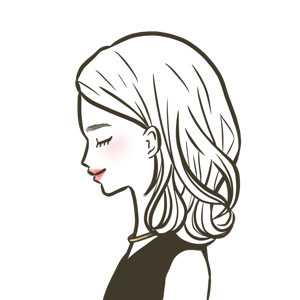
こちらの動画を参考に何回も見返してました…!
しかし、母乳外来では、
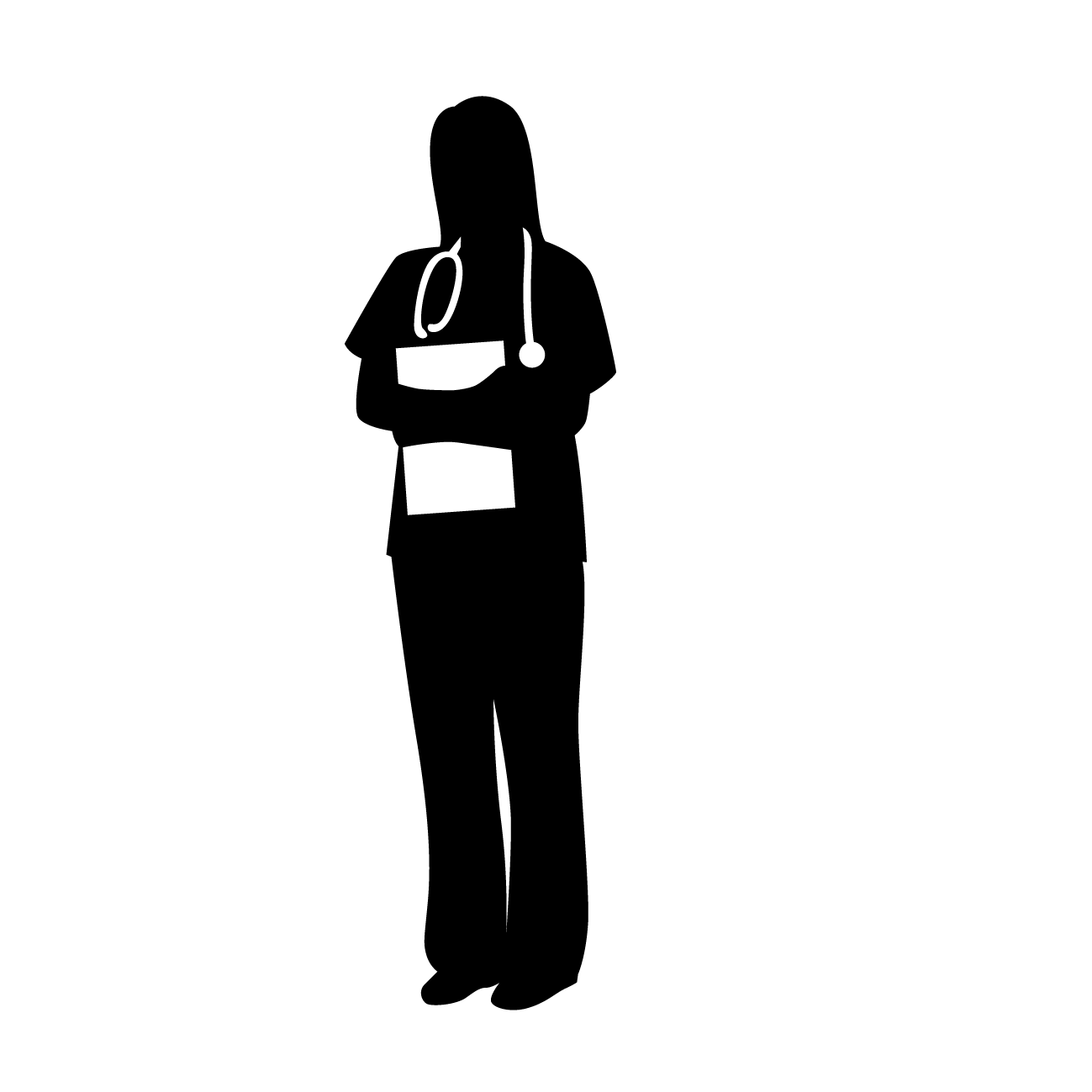
授乳間隔があきすぎるとおっぱいがたまって新鮮でなくなってしまいますよ。
それに、夜間授乳を辞めてしまうと、1日のトータル授乳量が減る分、昼間に頻繁にあげないといけないよ。
とのこと。
この時期になると、おっぱいは飲まれるときに作られる仕組みに変わるから、前もって作られてたまってしまってってことがなくなる…と事前に調べていました。
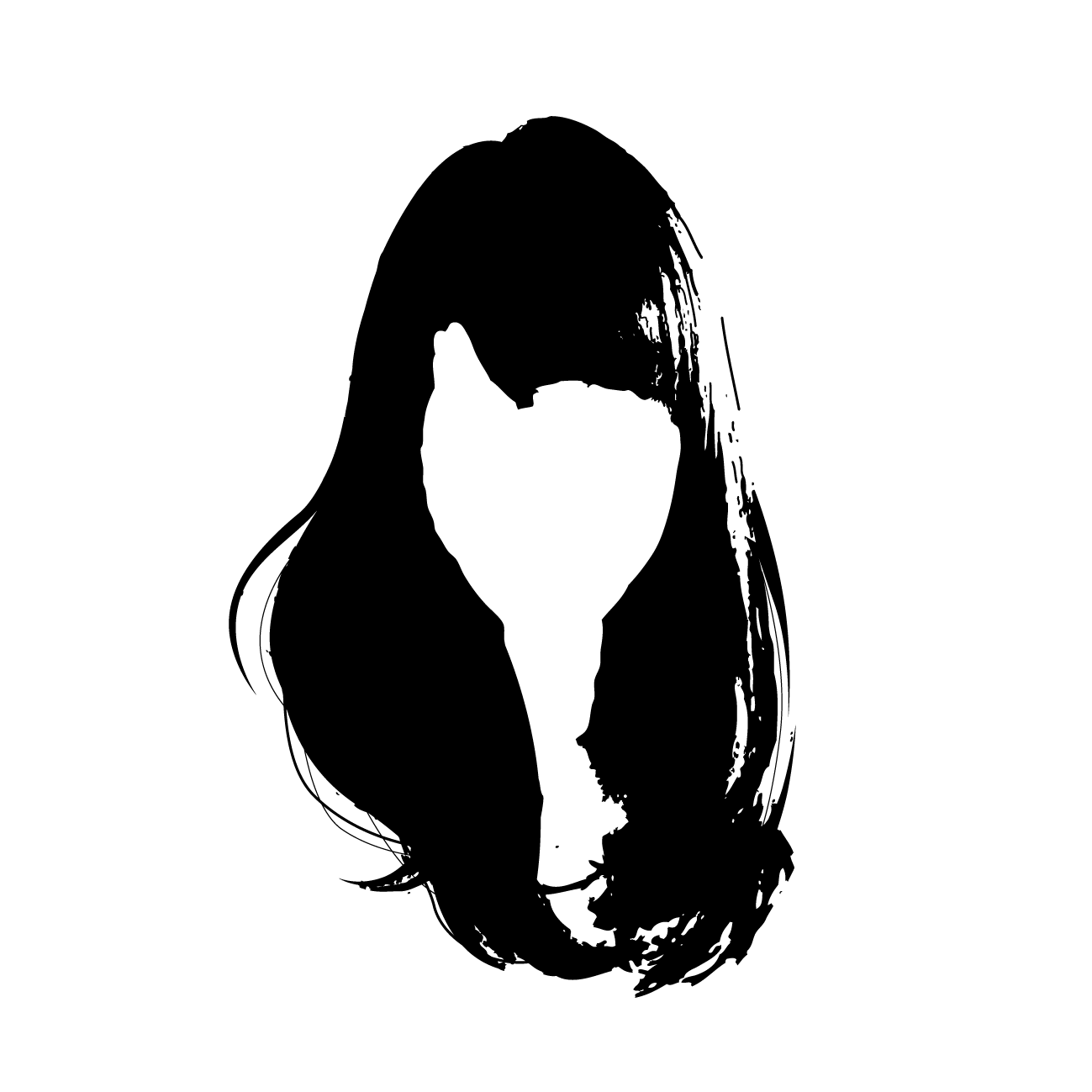
どっちが正しいのだろう…?
と母乳量は減らしたくないけど、夜間授乳は正直きつい…と、今後の対処を迷っていました。
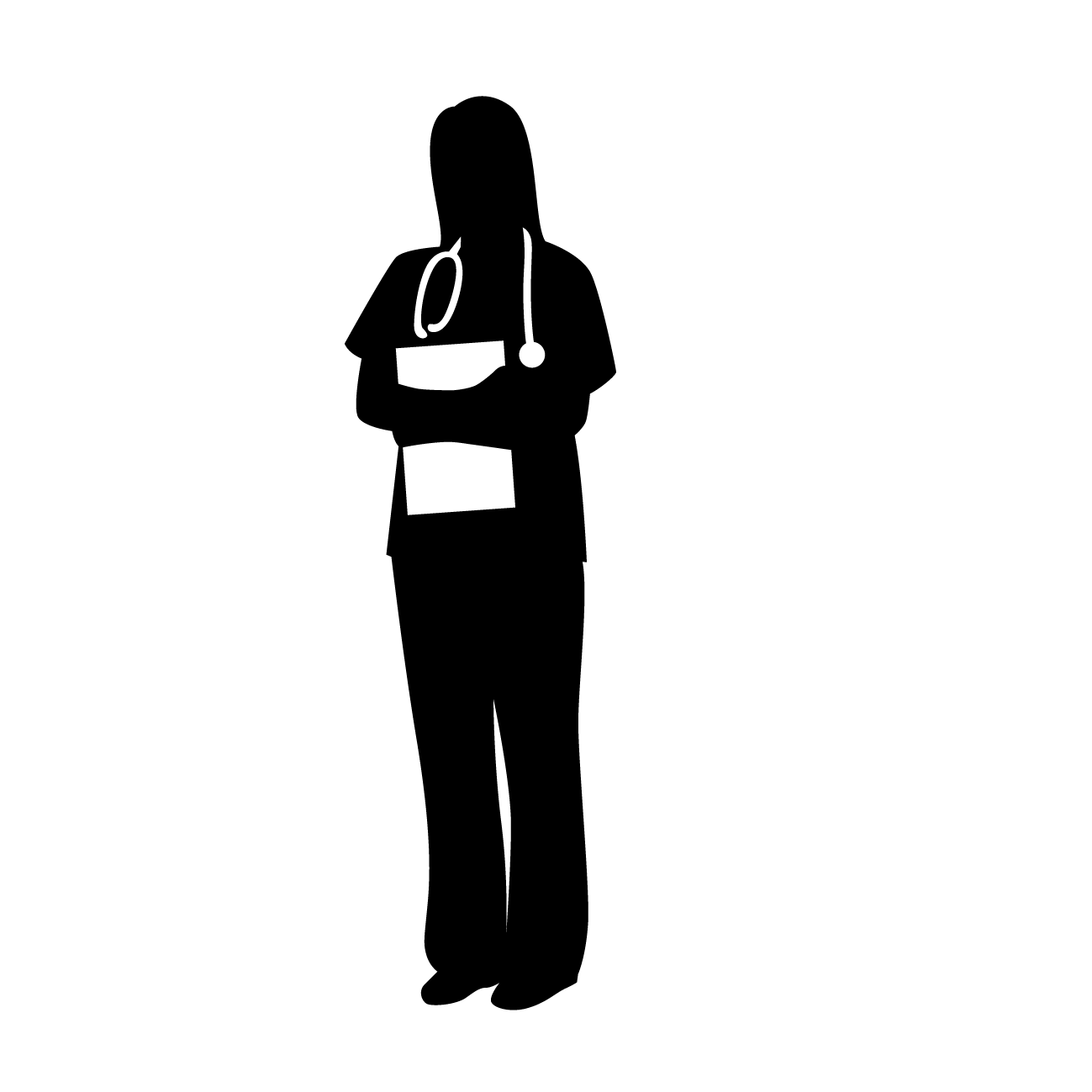
今は起きないかもしれないけど、発達に応じてまた夜泣きするようになることもあるしね。
そう言われると、いざという時に、授乳量が減って寝かしつけにおっぱいが使えなくなるのは痛い…。
一方で、4カ月になっても、ミルク500ml+母乳で、ミルクを足す量は増えもせず減りもせずの状態で、離乳食を食べる5~6カ月頃には母乳だけでいけるといいな、まだもうちょっと母乳量が増えるとうれしいな、という願望もありました。
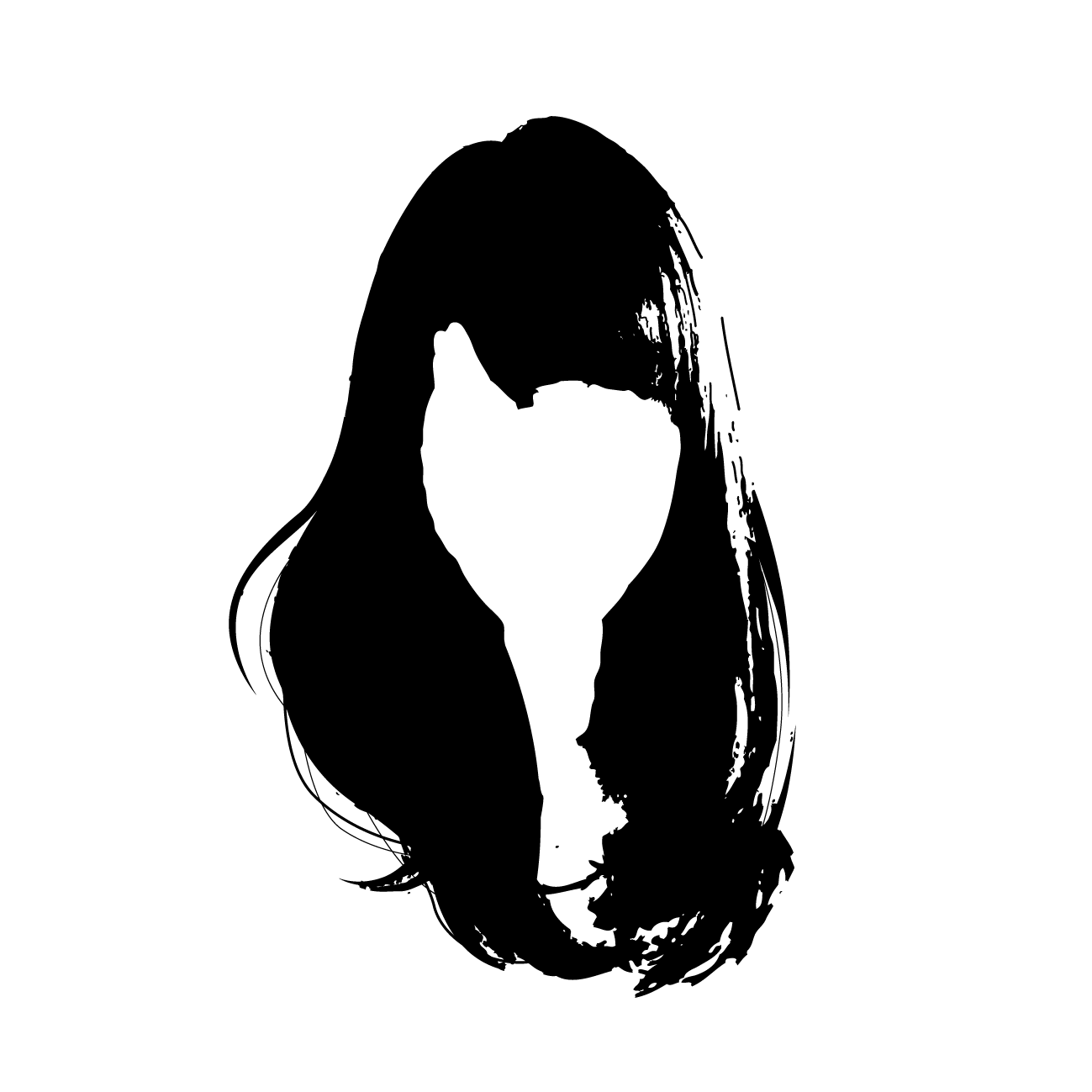
体は大きくなり哺乳量は増えるはずなので、ミルクの量が増えない=母乳量はちょっとは増えているのかな…?
それに、SIDS乳幼児突然死症候群は生後6カ月くらいまでが多いというので、夜中に長時間様子を見ないことも少し心配だったので、とりあえずもうしばらく頑張って夜間授乳を続けることにしました。
これまでは子どもが泣いたり、おっぱいが張ったりして目が覚めていましたが、この時期は3時間おきに目覚ましをかけて起きることに。
でも眠いので二度寝してしまい、授乳感が4時間開いてしまったりして、結構ストレスがたまりました。
あとは寝ている我が子を起こして、授乳して…そのあと寝ない!となった時、
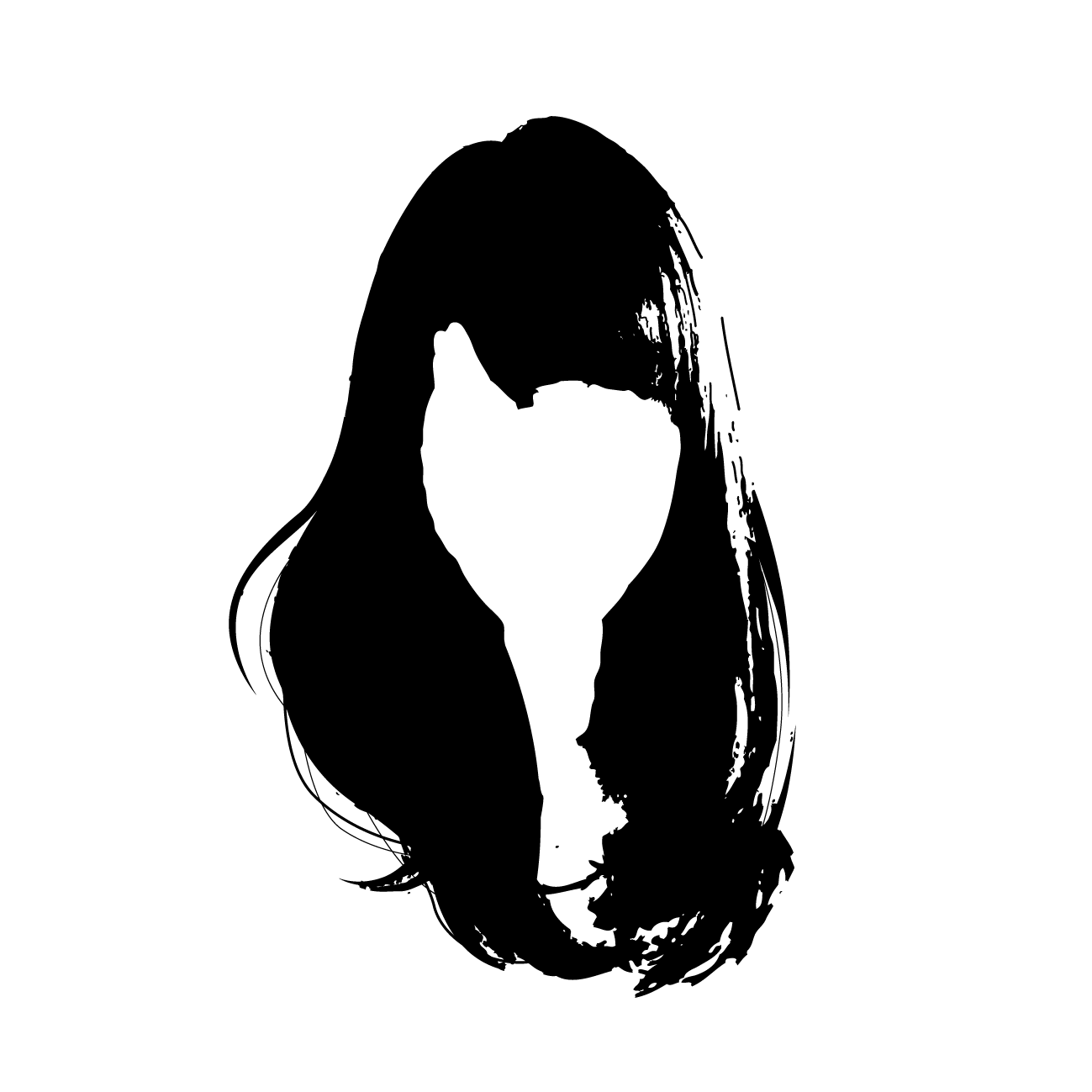
あのまま寝かせておけばずっと寝ていたかもしれないのに…
ともったいないような気持にもなりました。
しかし、辞める勇気とキッカケが足りず、母乳育児のメリットを信じて、もう少しやってみようと思った産後4カ月なのでした。
比較的安定した時期。勉強日和
振り返ると、この時期は授乳や生活のリズムも出てきて、比較的落ち着いていました。
確かに起きている時間はかなり長くなってきたし、寝ころんだ状態で方向転換してベッドから脱出するのを時折戻したりしなければならないことはあります。
が、寝てるか泣いてるかの新生児期とも違い、そのあと寝返りやずりばいを始めて動き回って目が離せないということもなく。
3カ月のころから始めた簿記の勉強も、思えば一番やりやすかった時期かなと思います。
勉強をする予定のないママも、出かけていくまではなかなか手間でも、家の中で筋トレやヨガなど、産後ダイエットにも取り組みやすい時期かもしれません。